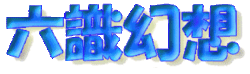pickup
最新記事
-
 アジア映画楽園の瑕 終極版 王家衛の射鵰英雄外伝「楽園の瑕きず 終極版」 原題は「東邪とうじゃ西毒せいどく:終極版」です。 「東邪とうじゃ西毒せいどく」とは、 金庸きんようの武俠小説 『射鵰英雄伝しゃちょうえ...
アジア映画楽園の瑕 終極版 王家衛の射鵰英雄外伝「楽園の瑕きず 終極版」 原題は「東邪とうじゃ西毒せいどく:終極版」です。 「東邪とうじゃ西毒せいどく」とは、 金庸きんようの武俠小説 『射鵰英雄伝しゃちょうえ... -
 アジア映画レジェンド・オブ・クロー/九陰白骨爪レジェンド・オブ・クロー/九陰白骨爪原題は『射鵰英雄伝しゃちょうえいゆうでん之九陰白骨爪きゅういんはっこつそう』です。 そう、金庸きんようが武俠小説の大家として...
アジア映画レジェンド・オブ・クロー/九陰白骨爪レジェンド・オブ・クロー/九陰白骨爪原題は『射鵰英雄伝しゃちょうえいゆうでん之九陰白骨爪きゅういんはっこつそう』です。 そう、金庸きんようが武俠小説の大家として... -
 アジア映画大英雄_香港・台湾のスターたちが天下五絶パロディ『大英雄』原題は『射鵰英雄傳しゃちょうえいゆうでん之東成西就とうせいせいじゅ』です。 そう、金庸きんようが武俠小説の大家として揺るぎない地位を築いたあの『射鵰英...
アジア映画大英雄_香港・台湾のスターたちが天下五絶パロディ『大英雄』原題は『射鵰英雄傳しゃちょうえいゆうでん之東成西就とうせいせいじゅ』です。 そう、金庸きんようが武俠小説の大家として揺るぎない地位を築いたあの『射鵰英...
仏教
論語
仏教
プロフィール
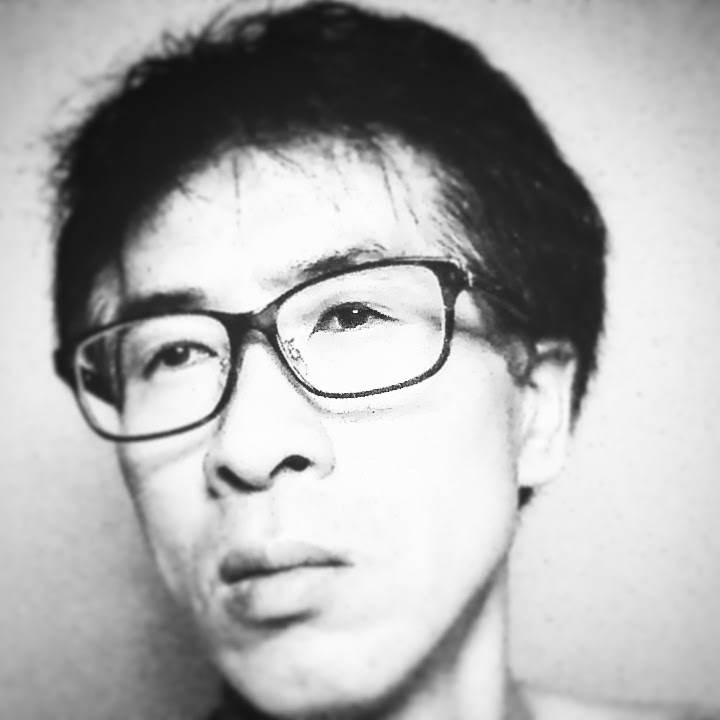
玉武士(タマブシ)
訪問して頂き
有難うございます。
日本思想、アート、
映画、生き方など
書いています。
読んで役に立てれば
幸いです。
それと
個人的ブログも
書いています。
有難うございます。
日本思想、アート、
映画、生き方など
書いています。
読んで役に立てれば
幸いです。
それと
個人的ブログも
書いています。
カテゴリー
西洋絵画論
映画遺産
西洋絵画論